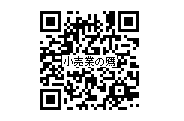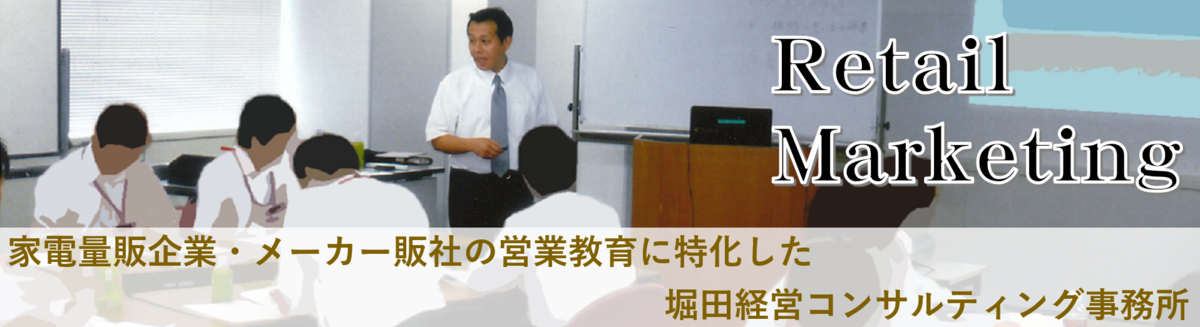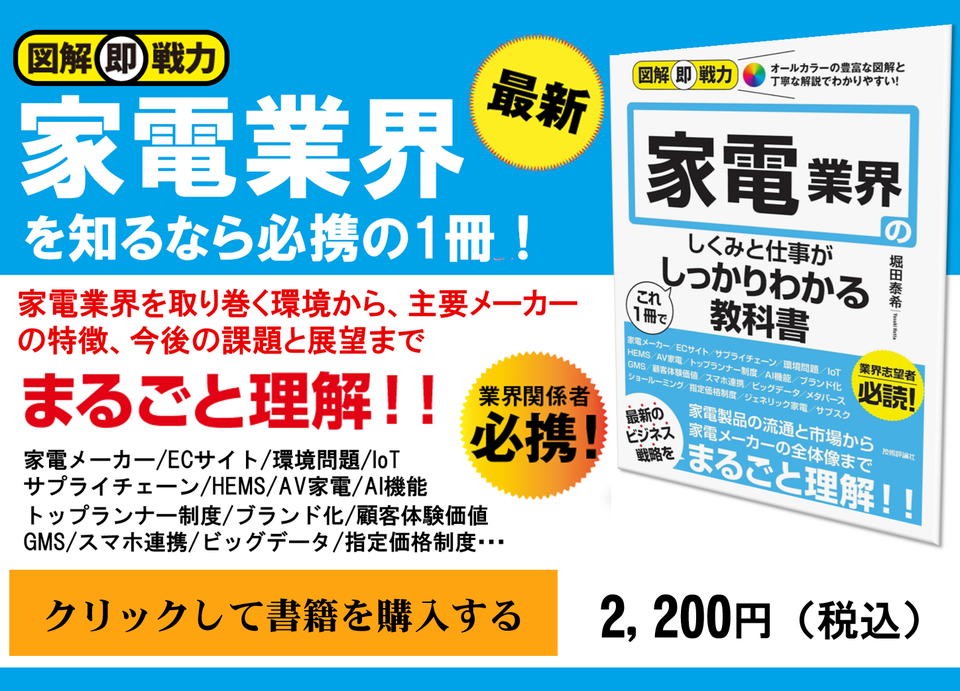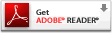家電量販店・家電メーカー・地域電器店の販売・営業・接客・売場作り・マーケティングの情報サイト

家電流通業界で働く「全ての人々」と「お客様」の幸せのために・・・
堀田経営コンサルティング事務所
090-4648-1616
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝)
陳列方法①
陳列(展示)方法を考える時に、一番大切なものは何でしょう?
それでは、まず、陳列(展示)方法で、必要なものを箇条書きで、整理してみましょう。
陳列(展示)方法で、考えるべきこと(広義)
①配置すべき場所
a)店舗全体の中での配置 → 通路展開の山積み展開含む
b)ゴンドラの中での配置
②配置場所までのサイン(誘導の仕方)
a)店頭からの誘導の必要性
③POP訴求について
a)POPの大きさの検討
b)振り上げPOPの検討
④価格設定
a)競合売価
b)市場売価
⑤装飾方法について
a)イメージ展開
b)量感展開
⑥商品の選定
a)利益重視型商品
b)販売数重視型商品
c)話題性の有無
d)季節感の有無
ざっと、書き出しただけでも、一つの陳列に関して、最低限このくらいの項目がでてきます。
ただ、残念なことに多くの小売業が、これらを「ごちゃ混ぜ」まぜにして、「経験」という不安定なもので処理してしまっているのです。
本当に、売れる陳列(方法)を考えるならば、「順序を追うクセ」をつけることが必要です。
先に、答えを示しますと、⑥の商品の選定から、全ては始まるのです。
何故なら、商品の選定無しに、配置や価格、POPや装飾・導線計画などが存在するハズが無いからなのです。
陳列方法②
前回は、⑥の「商品の選定」から、全ては始まるというところまで、お話しました。
数を売る商品なのか?、高額高利益の商品なのか?
恒常的に取り扱う商品なのか?季節(もしくは記念日)だけの取り扱い商品なのか?
取り扱う商品の上記特性を確認したうえで、その商品にあった展示場所・展示方法を考えねばなりません。
【数を売らねばならない(薄利多売)商品の場合】
数を売らねばならない = 多くの人に買ってもらわねばならない
当たり前の話ですが、多くの人に買ってもらわねばならない商品は、より多くの人の目にさらされねなりません。より多くの人の目にさらされるところ、それは何処でしょうか?
・入口付近、レジ前、主通路など、いろいろあります。
業種によって、少々の違いはありますが、基本は同じですので、一般的な基本をお話します。
①低単価で、ワンポイントの商品説明がいる可能性のあるものは、本来のコーナーにプラスして、レジ前、もしくはレジ上に訴求し、レジ係に、ワンポイント説明を教え、お客様がレジ通過時に一声掛けることが効果的です。
本来のコーナーでの訴求は、二通りの考え方があります。
1.主力商品として選定された商品の場合
本来のコーナーでも、陳列面の拡大(上下・左右に関する拡大)を図り、露出度をアップさせる。ゴンドラの「段抜き」で、上下に陳列面を拡大する時は、ゴールデンゾーンを中心に置くことが一般的です。
2.買上点数UPを狙って選定された「ついで買い」商品の場合
本来のコーナーでは、陳列面の拡大は行わず、主力商品への振り替えをスムーズに行うため、振り替えPOPを利用することで単価UPを狙います。
②低単価で、商品説明の不要な商品(セルフ商品)の場合、本来のコーナーにプラスして、レジ前での「プランター」展開や、主通路での「ワゴン」展開が効果的です。店内各コーナーの、接客テーブル横や柱周りにも「プランター」展開することも必要です。
本来のコーナーでは、大量陳列をすることが多いのですが、商品によっては、商品の内容物や現物のサンプル展示をすると、お客様の購入に際して、後押しを促進する効果が出てきます。
例えば、数年前に流行った「タイムスリップ グリコ」は、オマケをショーケース内に展示したことで、購買意欲を増大することが出来ました。
「店舗レイアウト図」があれば出して、売場に出てみましょう。
そして、入口からのお客様の動線がどうなっているかを実際に確認して見ます。入口が複数ある場合は、各入口の利用比率を必ず確認して下さい。
入口から入店された「お客様の後」を付いて行き退店されるまでの動線を複数回、経験することが大切なのです。
こうして得た「動線情報」をレイアウト図に記入します。
今、売らねばならない商品のコーナーにお客様は、立ち寄っていましたか?
全く、動線のなかったコーナーは、ありませんでしたか?
主通路の動線状況は、どういった感じでしたか?
こうした「生の客動線」は、色々なことを教えてくれます。現在の客動線を利用することや、あまりお客様が立ち寄らないコーナーがあれば、どの位置に「引き込みサイン」を訴求するかなどです。
陳列方法③
それでは、高額高利益の「付加価値商品」から始めます。
まず、高額商品には、次の2種類のタイプが存在します。
1.高額の高利益商品
2.高額の低利益商品 の2種類です。
1の「高額高利益商品」は、店舗として売って行きたい「主力商品」としての位置付けである場合が多く、メーカー側からすれば「商品力」・「話題性」に“完全な自信”が持てない「準主力商品」の場合が多いため、条件的(仕入値)に優遇する商品です。
それでは、高額高利益の「付加価値商品」から始めます。
まず、高額商品には、次の2種類のタイプが存在します。
1.高額の高利益商品
2の「高額低利益商品」は、競合関係で市場的に値崩れを起こしているものの、そこそこの台数が売れていたり、メーカーCMなどで一般的に認知度が高く、「展示せずにはいられない」商品の場合に多く見受けられます。
以上のことから、
「話題性のある商品は、仕入条件の優位性が認められず、供給面においても不安定である。」ということが言えます。
すなわち、こういった商品ばかりを売っていては「儲からない!」とい った状態に陥ってしまうのです。
店舗としては、同じ台数を販売するなら、高額高利益商品を売る方が儲かります。
従って、陳列方法では高利益商品を目立たせて、「話題性の強い高額低利益商品から、高額高利益商品に振り替える展示方法」が求められてくるのです。
では、その方法とは、おおまかには、次の3点が挙げられます。
①展示場所
②話題性の強い商品をとり扱っているという演出
③振り替えPOP
①の展示場所については、話題性の強い商品を利用する観点が必要になってきます。在庫金額の問題は、併せて考えねばなりませんが、出来うるならば、通常の商品群以外の「店頭」・「レジ前」など、人が良く目にする場所に「ダブル展示」を行い、当然のように「話題性の強い」商品を取り扱っているという演出が必要です。この「話題性の強い商品」を利用して、そのカテゴリーの売場に「お客様を引き込む」のです。
そして、お客様を引き込む「仕掛け」を創ったあとに、いよいよ、そのカテゴリー内の展示方法に取り組むことになります。
そのカテゴリー内の展示方法とは?
本当にシンプルな例を示します。
オリンピックの表彰台を思い浮かべてください。1位の選手が一段高く、2位・3位の選手よりも目立っています。これを売場内で演出します。
話題性の強い商品を「2位」の場所に展示し、ゴールデンゾーンにスペースを取って「1位」である「売りたい商品」を展示するのです。
ゴールデンゾーンについては、ここでは説明を割愛させて頂きますが、簡単には「目線」より少し低いところから、膝上までの位置を思い浮かべていただければ良いでしょう。それも、カテゴリー内の中央もしくは、エンド展開で訴求してみましょう。
ここで、以前からお伝えしている「客動線」が重要になってくるのです。
客動線を考えながら、「一番、お客様の目に触れる場所」を考えて、展示場所を決定するのです。
②の話題性の強い商品を取り扱っているという演出は、①のダブル展示に重複もしますが、POPの利用が効果を発揮します。
話題性の強い商品は、CM・車内吊り広告・雑誌などに取り上げられている場合が多いため、それを演出に使用し、店内でのアピールに用いることが必要です。
具体的には、「店頭」・「客動線の主要部」・「レジ前」にPOP化した訴求を行い、お客様の記憶に呼びかけるようにすることがポイントになってきます。
③の振り替えPOPは、最終のキーポイントを握っています。
まずは、「当店売れ筋No.1.2.3」のPOPを貼付し、当店では、この順番で販売台数が推移していることを、お客様に認知してもらうようにすることです。これは、実際に売れている順番を明記するのではなく、「売りたい順番」で訴求をすることになります。お客様を騙す結果になるという気持が湧いてくるかも知れませんが、一ついえるのは、「商品」を知り抜けば「自信」が生まれてきます。どの商品にも「特徴」は、必ず存在しますので、それをセールスポイントに持っていくには「商品知識」が、必要不可欠になってくるのは当たり前ですし、それによって「自信」が生まれてくるのも自然なことなのです。
その上で、「売りたい商品」の優越ポイント(独自ポイント)を箇条書きにしたPOPを貼付することです。
最後に、「矢印POP」などを用いて、「話題性の強い商品」との機能的な差、価格の差(高ければ、〇〇円UPで、この違いや、同じ金額で、この使い勝手の良さ!)などをアピールするのです。
但し、価格差は最高でも1.3倍に押さえねば、お客様の許容金額と掛け離れたものになってしまい、振り替えが困難になる場合が多くなるため、注意することが必要になってきます。
以上は、ほんの一例に過ぎませんが、今の販売については、自店が狙った商品を「どう、売っていくか?」という仕掛けが、必要不可欠になっていることを認識し、実行するといことが重要なのです。
是非、自分の店舗を以上のような観点から、見直していただければ「変更の必要性」を発見できることと思います。
家電業界のしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書 堀田泰希著
FABE商談設計【FABE分析:基本編】
あなたは、まだ本当のFABE分析に出会ってない
お客様が欲しているのは、商品を手に入れ、使用したときに得られる「感情」であり、商品はその感情を湧き立てる手段にすぎません。
この「感情」こそ根源的価値であり、それを考えるのがFABE分析ですが、現在のFABE分析の99%は不完全で本質にまで至っていません。
当事務所が独自の考え方でまとめた”FABE商談設計【基本編】”では、FABE分析の部分に特化してベネフィットの本質をわかりやすく説明しています。
当事務所へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
090-4648-1616
営業時間:月〜金 9:00〜18:00(土日祝定休)
※電話でのお問合せは上記時間外の場合、留守電話にてお受け致しております。内容を確認後、翌営業日以降にこちらからご連絡させていただきますので、お気軽にお問合せください。
スマホ用QRコード